遺伝? それとも育て方?
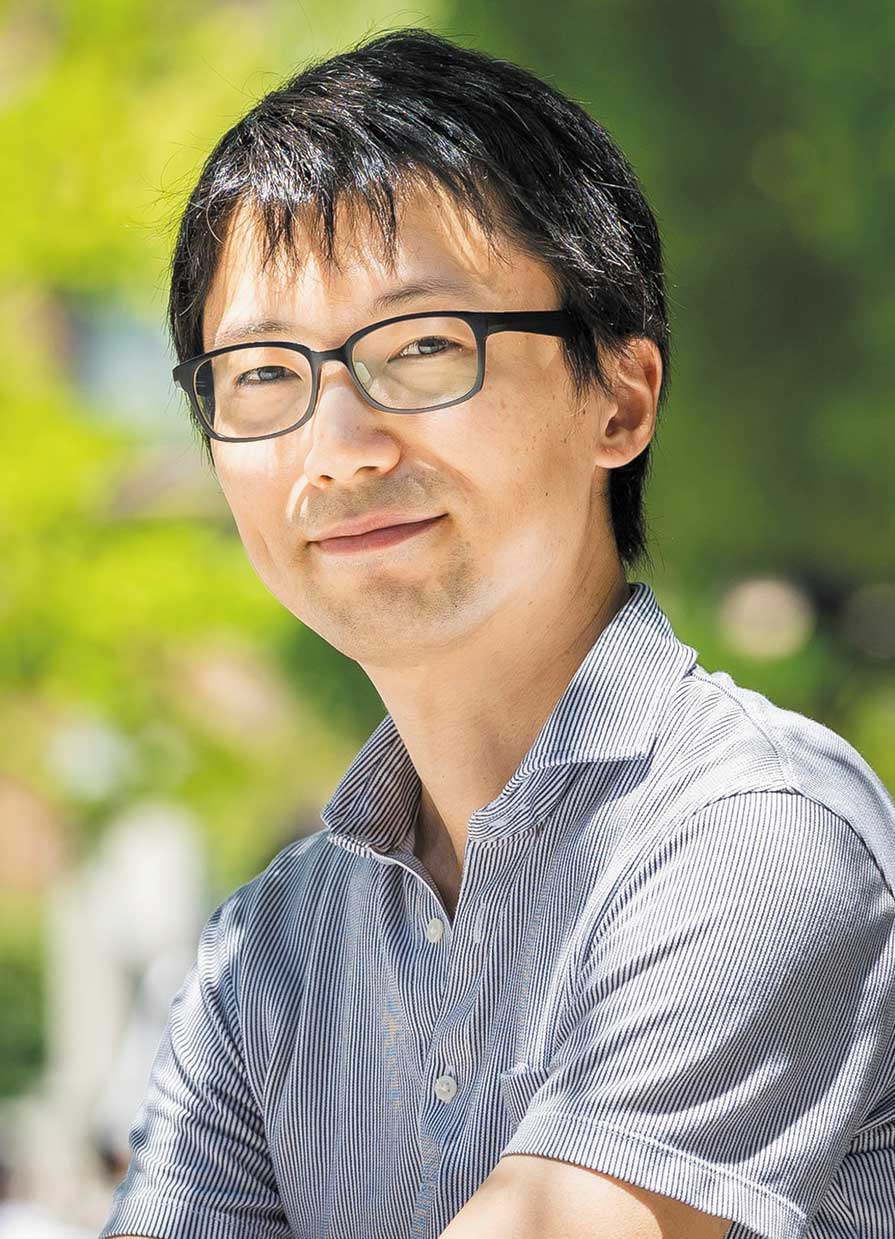
- 柴田 悠さん/社会学者
- 京都大学教授。専門は社会学、社会政策論。「『より多くの人々が幸せに生きられる社会』をつくるにはどうしたらいいのか?」という関心のもとで、「幸せ」「生き方」「親密性」「政策」などについて研究している。著書に『子育て支援と経済成長』等。
3人の子どもを育てている親として、私の本音は、「子どもの生涯の幸せのために、親が優先的に行うべきことを知りたい」ということだ。「子育てに絶対の正解なんてない」「子どもの特性によって答えは異なる」ということは分かる。でも、「一般的に優先すべきこと」を知りたいのだ。
安藤寿康著『教育は遺伝に勝てるか?』は、人生に対する「遺伝」と「環境」の影響を統計的に推定した膨大な科学的研究をふまえて、次のように結論づける。つまり、子どもに対して虐待や育児放棄をしたり、著しい貧困を強いたり、子どもの活動範囲を著しく制約したりすると、その子どもの成長や健康にとって重要な遺伝子が発現しにくくなってしまい、良い遺伝的素質も開花しにくくなってしまう。なので親が最優先すべきは、そのようなことをしないことだ、と。
実際、三谷はるよ著『ACEサバイバー』での調査によれば、子ども期に虐待被害などの逆境体験をより多く経験すればするほど、成人後に、貧困・病気・孤立・うつといった不利な状態になりやすい。またそのような不利は、子ども期に親以外の大人や友人等からのサポートがあれば、軽減されやすい。
よって親としては、周囲や行政の支援にも頼りながら、子どもに対して虐待や育児放棄をしないこと、著しい貧困を強いないこと、活動の範囲を著しく制約しないこと、そして他の大人たちや子どもたちにつながる機会を与えることが、まずは最優先だ。
さらに『教育は遺伝に勝てるか?』によれば、子どものIQ(知能指数)の個人差のうち、4割は「遺伝」、3割半は「共有環境」(同じ親のもとで育つ子どもたちが共有する環境、主に家庭環境)、2割半は「非共有環境」(子ども個人で異なる環境、主に家庭外環境)に起因する。また初期成人のIQは6割半が遺伝、1割半が共有環境、2割が非共有環境に起因する。知能に対する家庭環境の影響は2割~3割前後にすぎない。
さらに、親の個々の行動による影響はもっと小さい。たとえば「読み聞かせをしたり読書の機会を与えること」や「勉強しなさいと言うこと」は、低学年の小学生の成績(算数・国語)の個人差のそれぞれ5%ずつにしか影響していない。成績の5割は遺伝によるものであり、3割弱は非共有環境によるものとされている。
知能以外ではどうか。外向性や協調性では遺伝と非共有環境が5割ずつ、うつ傾向は4割が遺伝、6割が非共有環境で、いずれも共有環境(家庭環境)による影響はほぼない。
よって先の最優先事項の次にできることは、有意義な機会やきっかけを与えることくらいだ。本人の素質や気持ちに反する無理強いはしないように気をつけたい。
(無断転載禁ず)

