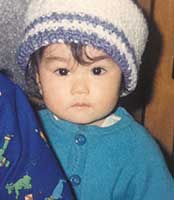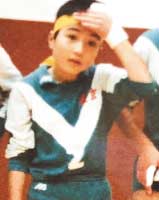挫折・31歳でコメディスクール入学 「バブリーキャラ」からマルチタレントへ

- 平野 ノラさん/お笑いタレント
- 1978年生まれ、東京都出身。31歳のとき、本格的に芸人の道に進み、ド派手なメイクと巨大肩パッド入りの赤のボディコン、携帯電話を提げた「バブリーネタ」で大ブレイク。近年は、テレビ・ラジオを中心にタレントとして活躍するほか、片付け本『部屋を片づけたら人生のミラーボールが輝きだした。』(KADOKAWA)を執筆。特技はバレーボール。趣味はダンス、絵画など多彩。42歳で第1子出産。2026年公開予定の映画『あなたの息子ひき出します!』で映画初出演。
大人になるのが楽しみだったバブル時代
ド派手な巨大肩パッド入りの赤のボディコンに身を包み、ソバージュヘアに太眉、肩から携帯電話を提げた「バブリー芸人・平野ノラ」がお茶の間に知っていただくようになったのが約10年前。そこからさかのぼること二十数年前の1980年代後半は、まさに昭和のバブル景気真っただ中でした。
団地住まいでしたが、父は不動産業で急に羽振りがよくなり、近所の女性はアッシーくんが車で迎えにくるようになりました。小学生だった私は、世の中が活気にあふれ、大人たちがはしゃいでいる姿を目の当たりにして、「私もいつかああなるんだろうな」と、大人になるのを楽しみにしていたことを覚えています。
バレーボールで鍛えられた強さ
一方の私は、母がママさんバレーをやっていた影響から、小学3年生のとき、バレーボールのクラブチームに入るのですが、全国制覇を成し遂げるような強豪チームで、毎日、厳しい練習・指導に耐えていました。礼儀に始まり、心技体、全てたたき込まれました。遠征や合宿のおかげで食べ物の好き嫌いはいまだにありません。監督、先輩の言うことにはすべて「はい」、頭はスポーツ刈りで、その後、中学、高校までバレーボール漬け。バレーで鍛えられた精神的な強さがあったからこそ、芸能界でもやってこれていると思います。
中高の6年間はキャプテンも務めました。笑いに目覚めたのは実はその頃。といっても、練習がつらすぎて、チームメートと笑い合う瞬間に癒やしと救いを感じたのがきっかけです。「キャプテンとして盛り上げなきゃ」という気持ちから、冗談を言ったりモノマネをしたりするとみんなが笑ってくれて、少しだけ気持ちが楽になった。そのとき、笑いが持つ力ってすごいと思ったのです。
夢をあきらめるたびお笑いに近づいていた
だからといってすぐにお笑い芸人になろうと思ったわけではありません。中学生のとき、ミュージカル『アニー』を見てエンタメの世界に憧れ、高校卒業後、ミュージカルの専門学校に見学に行ったんです。しかし、小学生たちが生き生きと歌い、ダンスを踊る様子を見て、「私は遅かったんだ」と気づきました。私がバレーボールに打ち込んでいた時代を、この子たちはミュージカルに時間を費やしているんだと思い知らされ、あきらめがつきました。
ダンスだけならなんとかなるかもしれないと、次にダンスの学校に通いましたが、そこでも結局は同じ理由で挫折。その後、友達が旗揚げした劇団に客演という形で出演させてもらいました。ところが、ウケを狙って台本に書いていない台詞(せりふ)を言い、会場は盛り上がったものの、演出家からは「勝手なことをするな」と怒られて、自分は集団には向いていないと実感。「そうか、一人なら迷惑をかけない」と思った先に、ついに「お笑い芸人」の道を発見しました。
ただ、そのときは、ネタのつくり方もわからず、オーディションを受けても、自分が面白いと思うことを並べるだけで、審査員には「お笑いに向いてない」と言われてしまいました。「じゃあ、相方が必要かもしれない」と探し、ライブにも出てみたものの解散。うまくいかずに、25歳でお笑いを一旦あきらめることになったのです。
ガラクタを捨てたらお笑いが残っていた
そこから就職してOLになったり、派遣社員になったり、父の仕事の関係で不動産の宅建資格を取ったりしてみたものの、自分が何をやりたいのか、どんどんわからなくなっていきました。25歳からの数年間は自分にとっての暗黒時代。いろんなことに手を出しては辞め、引きこもり、ものに依存するようになり、結果的に家の中にものが溜まっていって、足の踏み場もない汚部屋になっていったのです。
当時、結婚を前提に付き合っていた彼氏と同棲し、食べさせてもらっていた時期もあります。「だったら、家庭に入れば幸せになるのでは?」とも思いましたが、そうじゃなかった。やっぱり自分を幸せにするのは自分しかないと気づいたとき、ある本との出合いがあったんです。『ガラクタ捨てれば自分が見える』(カレン・キングストン著)という片付け本を読んでみたら、「家のありさまと心はリンクしている」と書いてあって、もう驚愕で。
ものが何もなくなったときに、自分と向き合うことができ、お笑いに未練があることがわかりました。売れる、売れないは別にして、本当にやりたい気持ちが明確になり、「再チャレンジしないと死んでも死にきれない」と。彼とも別れ、最小限の荷物を持って一人暮らしを始めました。親には「孫の顔を見せられなくてごめん」と謝って、31歳にしてコメディスクールに入ったのです。
運命のオーディション 緊張で手が震えた
10個以上歳の離れた同期たちに混じって、「ババア」と言われながらも本格的にお笑いを学んだ時期は、猛烈にやる気もあり、「第二の青春」でした。お笑いのセオリーも理解し、楽しくて仕方ない。いつも最前列で食い入るように講師の話を聞いていました。
スクールに一緒に入った元バレー部の相方は美人で、先生方の期待も高かった。これならデビューも近いと思いました。ところが、その相方が突然辞めてしまい、初舞台の出演チャンスを失いかけたんです。でも、ここで初舞台を逃したら遅れを取ってしまう。だったら一人で舞台に立とうと、「とにかくオーディションだけでも受けさせてください」と直談判しました。
この壁を乗り越えない限り先へは行けないと、必死の覚悟で臨んだオーディションは本当に緊張しました。手は震え、冒頭の台詞(せりふ)も忘れてしまったぐらい。でも何とかクリア。私にとってこのオーディションは、25歳でお笑いを挫折した自分に勝った人生の大一番だったかもしれません。初舞台本番になると、度胸だけは人一倍あるので、冷静に自分のお笑いができました。教務の先生にも「お前、おもろかったな」と言っていただき、自信がつきました。
念願のブレイク! 断捨離で人生が好転
その後も、「バブリーキャラ」でブレイクするまでの4年間は、紆余曲折がありました。ヘルメットですべての男を落とせるキャラをはじめ、モノマネやバブルのキャラクターで仕事が少しずつ増えてはいたものの、「ネクストブレイク枠」が2年続いた。どうすればブレイクできるか向き合ったときに「自分が武器だと思っていたものが、足かせになっていた」と気づいたのです。
当時バブルキャラで受かるオーディションもあれば落ちることもあり、戦略としてネタを使い分けていた。でも「たった一つのキャラと心中する覚悟がなければ、これ以上売れない」と、勇気を出し、バブルキャラ以外のネタや小道具全て処分しました。覚悟が確信へと変わった瞬間でした。
残った一つをブラッシュアップし、徹底的に磨き上げたのが、みなさんもよくご存じの「OKバブリー!」「しもしも~?」です。あとは神頼みしかないと、伊勢神宮にもお参りし、翌年念願のブレイク!
片付けはモノを通して人生を好転させるだけの価値があることを、身をもって知りました。
一発屋で終わらないための戦略とは?
しかし、「バブリーキャラ」も毎日見ていたらいつかは飽きられます。「この芸風にしがみついていたら、一発屋で終わってしまう」という懸念は売れたときから持っていました。最終的に目指していたのは「マルチタレント・平野ノラ」です。いずれはキャラを脱ぎ捨て、素の私で勝負していかなければいけません。
少しずつ変化し続ける必要がありました。毎日テレビに出演する中で、まずは巨大な肩パットから綿を少しずつ抜き、眉毛をだんだん細くし、メイクも薄くしていきました。「敵をあざむくにはまず味方から」と言いますが、マネージャーにも気づかれないぐらい徐々にバブリー色をマイルドに変化させ、最後にあの大きな携帯電話も封印すると、ランジェリーのCMなど、これまでなかったような新しい分野のお仕事が広がっていったのです。
今も求められれば「バブリーキャラ」は復活しますし、台本を読んで、「この仕事はバブル50%でいこう」なんて落とし込み方もできるようになりました。これも日頃、素の平野ノラとしてお仕事させていただけているおかげだと思っています。
やっとわかった!人生に無駄なものはない
ほかにも、片付け本を執筆してから、片付けに関するお仕事の依頼を受ける機会が増えました。また、38歳で結婚し、42歳で母親にもなったので、子育てや育児のお仕事の幅も広がりました。また、芸能人初の日本バレーボール協会の評議員も務めさせていただき、バレーボール関係のお仕事も増え、大好きなバレーに恩返しできる喜びをかみ締めています。
そう考えると、これまで自分が挫折してきたこと、つらかった経験はすべて無駄じゃなかったと思えます。バレーボールがあったからメンタルが強くなり、ダンスを学んだから「バブリーダンス」も踊ることができ、一度はお笑いを挫折し、汚部屋に引きこもった経験があったから片付けに目覚め、もう一度お笑いを目指すことができました。この紙面を読んでくださっているみなさんも、過去を振り返ってみれば、人生に無駄なものなど何一つないことに気づかれるのではないでしょうか。
特に片付けは、単にものを片付けるのではなく、自分自身を知るきっかけにもなるアクションです。生きている限りものは増え続けますが、節目、節目でものを見直し、いつまでも自分らしさを大切にしていただきたいと思います。
(都内事務所にて取材)
(無断転載禁ず)