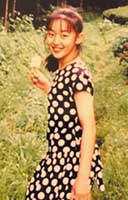静岡の茶畑…、中山美穂のファン…、アイドル…、 好奇心…、フィリピンのスラム…、女優

- 酒井 美紀さん/女優・タレント
- 1978年生まれ、静岡県出身。93年、歌手デビュー。95年公開の『Love Letter』で俳優デビュー。日本アカデミー賞新人俳優賞に輝き、注目を集める。96年にはドラマ『白線流し』の主人公・七倉園子を演じる。私生活では2008年に結婚、10年、長男出産。俳優業と並行して、07年より国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパンの親善大使、21年より不二家の社外取締役を務めるなど、多方面で活躍。23年、東洋英和女学院大学大学院国際協力研究科修士課程を修了。シャツ:ナゴンスタンス、ピアス、リング:ブランイリス(ブランイリス トーキョー)
お茶畑で茶摘みをした家族との思い出
私はお茶で有名な静岡県の出身です。実家は茶畑のある兼業農家。父はサラリーマン、母も外で仕事をしている共働きでしたが、祖父母が山間部でお茶の栽培をしていて、幼い頃から自然の中で育ちました。
春、家族総出で行う茶摘みの季節になると、いとこたちも一緒に山に登り、手摘みを手伝うこともありました。茶畑は山の上の方の斜面につくられています。山間なので、そうしないと太陽の光が当たらないのです。麓からそこまでは40分ほど。行くのは大変でしたが、家族、親戚の絆を育む行事だったように記憶しています。
その後、祖父母の代の畑は閉じましたが、今は父が自分の茶畑と共に、近所の跡継ぎのいない別の畑の管理を頼まれ、お茶栽培を続けています。ただ、父も70代半ば。日本の農業の高齢化や跡継ぎ問題を実感するところです。
芸能界入りの原点は子どもミュージカル
10歳の時、静岡市制100周年の記念事業として行われた「子どもミュージカル」のオーディションに合格して出演。半年にわたって練習を重ね、舞台に立ちました。今、振り返れば、この経験が「女優になりたい」という夢を明確にしたと思います。
そこから演技を学べる場所を探し、浜松のスクールに通い始めました。入学後は歌と芝居の両立を目指すことになり、ボイストレーニングも学び、13歳の時にスカウトされて芸能事務所に所属します。
私は子どもの頃から中山美穂さんが大好きで、憧れの存在だったのですが、中山さんが活躍された80年代は、アイドルでありながらドラマにも出演するのが定番でした。中山さんは最も輝いていたアイドルの1人だったと思います。
そして、時代を追いかけるように、私自身も15歳でアイドル歌手としてデビューすることになるのです。
映画『Love Letter』で女優としてブレイク
その後、高校2年生の時、映画『Love Letter』(岩井俊二監督)で女優デビュー。中山さんの少女時代を演じる役をオーディションで獲得しました。憧れの中山さんが主役だと知ったのは、実はオーディション当日です。
でも、当時はアイドルとして全国をキャンペーンで飛び回っていて、「今、自分は何県にいるんだっけ?」というぐらいの忙しさでした。その合間のオーディションということもあり、また、オーディション慣れしていないのが幸いしたのか、舞い上がる間もなく、渡された紙に書かれたセリフを読んで、おしまい。
もう1回、呼ばれた時に初めて岩井監督とお会いし、静岡での生活についてたくさん聞かれました。それからしばらくして「合格」を頂いたものの、「雑談しかしていないのに?」と、ちょっと不思議な気持ちでした。
映画のロケ地は北海道で、静岡の実家から通いました。私は、早く東京に行って1人暮らしをしたいと思っていましたが、デビュー後も「高校卒業までは親元で」というのが事務所の方針だったのです。ただ、静岡は東京から近いといっても、実家は静岡駅からは車で40分ほど。両親には朝早く、夜遅くに駅まで送迎してもらい、ずいぶん迷惑をかけたと思います。
ちなみに、中山美穂さんとは1日だけ同じ撮影日がありました。うれしさと緊張のあまり、会話の記憶はほとんどありませんが、夢のような共演をきっかけに、“女優”をさらに強く意識するようになりました。
『白線流し』のあと、25歳で芸能活動を休止
映画のあとは、ドラマ『白線流し』でヒロインを務めることになり、自分がやりたかった仕事をこんなにも早くできるようになって、充実した日々でした。15歳でデビューしてから10年間、正直、お休みはあまりありませんでしたが、若さもあったので体調を崩すこともなく、「休みはいらない」と思っていたぐらい。どんなに走り続けても楽しかったんです。
でも、自分のなかにあるものをアウトプットし続けて25歳を迎えた時、「私はそろそろインプットしなければいけない時期にきている」と感じ、芸能活動を一旦休止。ニューヨークへの語学留学を決めました。
事務所はもちろん大反対。さらに、長期間休んで戻ってきた時、私の居場所はもうないかもしれません。それでも行こうと思ったのは、英語の習得だけでなく、エンターテインメントのメッカ、ニューヨークで演技も学びたかったからです。どうせ行くなら熱量が高い時に行きたい。そんな前向きな気持ちが自分の背中を押し、不安はまったくありませんでした。
ニューヨーク留学は人生の転機
私の人生において、たった1人で海外で暮らした経験は、大きな転機になりました。
意気揚々とニューヨークに乗り込んだものの、生活の基盤を整えるのは並大抵ではありませんでした。部屋を借りるにも、銀行口座を開くにも、語学力が足りないばかりか、日本とはシステムも文化も違い、何一つ思った通りにいきません。壁にぶつかるたび、涙を流すことも多かったですが、誰にも頼れない環境で生きていく力を得た経験は、それに勝るものがありました。
生活が落ち着いてからは、英語とお芝居の勉強に明け暮れました。日中は学校、授業が終わるとブロードウェイの舞台を安い当日券で観劇し、夜は演劇やダンスの講座にも通いました。
また、その合間にはボランティア活動も積極的にやりました。現地で出会った日本人コミュニティを通じ、小児の心臓移植のために渡米してきた日本人親子の生活支援ボランティアに参加。ほかにも何家族かの生活サポートや話し相手をするうち、仲間たちとボランティア団体『Heart to Heart』を立ち上げるまでに。患者家族の心の支えになりたいという思いから、手づくり石けんを販売して寄付金を集める活動なども行い、この体験が、のちの国際協力活動の原点となったのです。
帰国後、俳優業と並行し国際協力の道へ
約1年半の留学を終え、帰国後は再び俳優活動を続けながら、国際支援にも関心を持つようになりました。
ある時、テレビ番組の取材でフィリピンのスラム街を訪れ、ゴミを拾って生活する少女の姿を目の当たりにして思ったのは、「無力感」でした。世界には本当に貧しい生活を強いられている子どもたちがたくさんいます。自分1人では世界を変えられない。でも、せめて私にも何かできることはないか?と考えていた時に出合ったのが、国際協力NGOワールド・ビジョン・ジャパンのチャイルド・スポンサーシップです。
そして、継続的な支援を続けるなかで、2007年、同団体から依頼を受けて親善大使に就任。以後、18年以上にわたって支援活動に携わっています。支援地域の視察や報告イベントでの広報活動、映像のナレーション、ラジオ番組でのPRなど、支援の現場を伝え、支援の輪を広げることに尽力しています。
大学院での研究「演劇×国際協力」
しかし、世界中でNGOが活動しているのに、紛争や貧困は減らないどころか、マクロで見ると増えているという現実があります。「それは、なぜか?」という疑問に対して、私自身の経験だけでは答えが出ないと考え、40歳を過ぎてから、大学院で“学問”としての国際協力を学ぶことにしました。
研究テーマは「演劇を通じた社会的包摂(社会的に排除されている人々を社会に取り込み、支え合うこと)」です。発展途上国では、識字率の低さから、文字ではなく応用演劇を使って防災教育や啓発を行う事例が多いことに着目しました。例えば、バングラデシュではサイクロン防災を劇で伝えたり、南米ではフォーラムシアターといって、観客も参加して社会問題の解決策を導き出す討論型演劇があったりします。
私も長年やってきた演劇が、社会が抱える課題を少しでも改善していくツールになるかもしれないと、「演劇の社会的役割」を体系的に研究しました。今後も社会と演劇の新たな関係を模索し、将来的にはメソッドにまとめて、国際協力に生かせればと思っています。
演劇の歴史は古く、日本では700年代から“神事”として存在していたと、日本最古の史書『日本書紀』に記されています。それが今も形を変えて社会と関わり続けていることに、私自身、誇りを感じています。
社外取締役としての活動と視点
大学院在学中、企業の社会的責任であるESGやSDGs(持続可能で豊かな社会の実現を目指す取り組み)への関心を深めていたのですが、老舗菓子メーカーの不二家さんから社外取締役のお話を頂いた時はびっくりしました。
近年は特に、企業のガバナンス改革(会社の健全な成長のため、ルールを整え、皆で守ること)が進み、取締役会における多様な視点を経営に生かす流れがあるなかで、ESGやSDGsは、私が研究する国際協力の柱ともいえるものです。
そういった学問的知識はもちろん、NGOワールド・ビジョン・ジャパンでの活動、女優、母など、自分が関わってきたさまざまな世界観を総動員して少しでも役に立てるならと、お引き受けすることにしました。
もちろん勉強しなければいけないこともたくさんありますが、経営塾に行って企業のトップの方にお話を伺ったり、数字の裏側を考えたり、視点を変えて未来を見つめることで、また別の世界が広がる面白さも感じています。
分からないことを知るのは、とても面白いこと。いくつになっても好奇心を失わず、この先も自分らしく、学びや挑戦を続けていきたいですね。
(都内にて取材)
(無断転載禁ず)